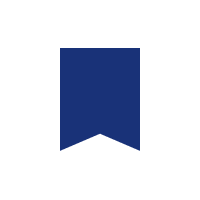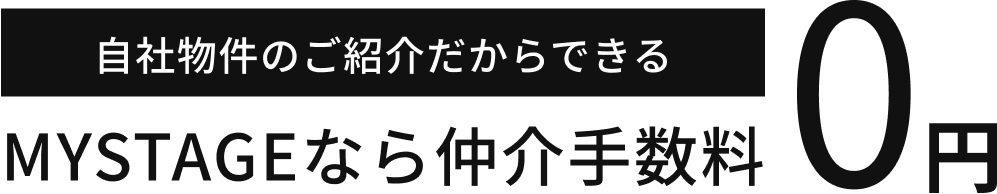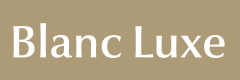MYSTAGE
ABOUT MYSTAGE
MYSTAGEについて
首都圏で一番売れている
リノベマンションARISEの
売主直販サイトです
リノベマンションARISEの
売主直販サイトです
物件の仕入れから販売までを行う
売主会社だからできる手厚いサービスで、
お客様の住まい探しをサポートします。
売主会社だからできる手厚いサービスで、
お客様の住まい探しをサポートします。






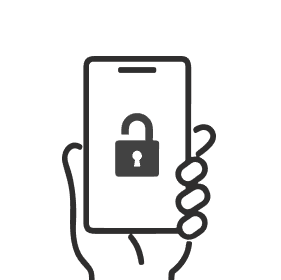

どんな時も自分らしくいられる空間であること。
高品質な住まいづくりとアフターサービスで
末永く暮らしを守ること。
そして、環境や社会問題に対しても配慮すること。
アライズは住む人を第一に考えて生まれた、
時代の先を行くリノベマンションです。
高品質な住まいづくりとアフターサービスで
末永く暮らしを守ること。
そして、環境や社会問題に対しても配慮すること。
アライズは住む人を第一に考えて生まれた、
時代の先を行くリノベマンションです。
どんな時も自分らしくいられる空間であること。高品質な住まいづくりとアフターサービスで末永く暮らしを守ること。そして、環境や社会問題に対しても配慮すること。
アライズは住む人を第一に考えて生まれた、時代の先を行くリノベマンションです。
アライズは住む人を第一に考えて生まれた、時代の先を行くリノベマンションです。
ARISE CONCEPT
安心の保証
RELIABLE

業界最高水準の10年保証※をはじめとする、充実の保証で不安を払拭
※専有部の給排水管・ガス管

ユーザーファーストプランニングが心地良い住まいをつくる
快適な設計
COMFORTABLE
カスタムオーダー
CUSTOM ORDER

オプション工事で叶える、理想の“自分らしい”暮らし方

SEARCH
ARISEを探す
掲載物件はすべて仲介手数無料。理想の住まい探しをARISEコンサルタントがお手伝いします。
キーワードから探す
まとめて探す
新着物件

ABOUT US
エフステージのサービス
物件の仕入れから内装、販売までを手がける売主会社の私たちだからできる、住まい探しにとどまらないサービスで理想の暮らしをサポートします。
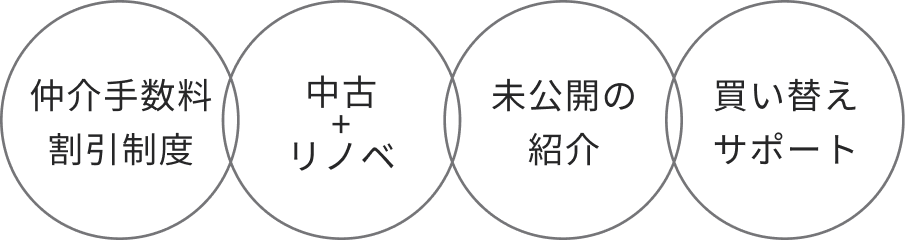
01


未公開物件の
ご紹介
02
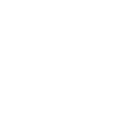
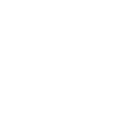
ローン
相談
03
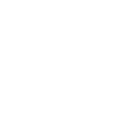
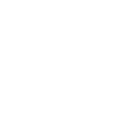
各種
メール通知
04


お気に入り
登録